FAMILY
サンタとお母さんとぼく
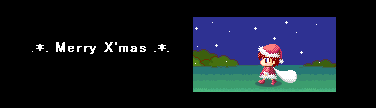
ぼくはたぶん不幸な子どもです。
というのも、今日はせっかくのクリスマスなのに、お母さんとお父さんにおいてきぼりにされて、おるすばんをしなければならないからです。
「僕がいるからいいじゃない」
と、兄はそういって、ぼくをなぐさめてくれますが、ぼくのりそうのクリスマスは、お父さんなんてどうでもいいから、お母さんと兄との三人ですごすたのしいクリスマスなのです。
ごちそうやケーキやツリーなんてどうでもいいのです。
だから、せっかくお母さんがおるすばんをするぼくらのために、いっしょうけんめい作ってくれたごちそうも、ケーキも、ツリーのかざりもなんだかむなしいだけです。
今日は、お父さんとお母さんはデートなのです。
クリスマスの日は、お父さんたちにとってはとくべつな日で、恋人どうしになったのも、けっこんしたのもこの日なのだそうです。
だから今日、この日だけは、お母さんは、ぼくらのお母さんを止めて、お父さんの恋人にもどるのだそうです。
きれいにお化粧をして、きれいな服をきたお母さんは、子どものぼくから見てもドキドキするくらいにきれいでした。でもきれいすぎて、いつものかわいいお母さんとはちがう人みたいで、ぼくは何だかとても悲しくなってしまいました。
そして、
「じゃあ、行ってくるね」
とニコニコ、えがおで言ったお母さんの目の中にもうぼくはいなくて、目の前のお父さんしか見ていませんでした。
それを見ていたぼくは、何だかとてもさびしくなってしまいました。
あんまりぼくが落ちこんでいるので、兄が車でドライブに行こうかとさそってくれました。
ぼくも、家の中でこうやってすねているのも、ひせいさん的だと思ったので、「いいよ」と言いました。
でも外はもう雪がチラチラふってきていて、いくら小さいころからカートでならしているとは言え、めんきょをとったばかりの兄のうんてんでは、まだ峠をせめるのは早いと思ったので、ぶらぶらと市内を走ったあと、しぶかわ市の文太おじいちゃんの家へ行くことにしました。
文太おじいちゃんは、お母さんのお父さんで、小さなおとうふ屋さんをしているのです。
ぼくは小さいころからこの文太おじいちゃんのことが大好きだったので、きっと兄は、おじいちゃんと会うことでぼくを元気にさせたいと考えたのだろうと思います。
ぼくらが行くと、おじいちゃんはいつものように家でタバコをすいながらお酒をのんでいました。
「おう、来たのか。まあ、上がんな」
ちょっとお酒くさいおじいちゃんは、ぼくらの顔をみたとたん、ニコニコとえがおになってぼくらをむかえ入れてくれました。
「うちにはごちそうもケーキも無いからな。これで勘弁してくれや」
そう言って、ニコニコ顔のおじいちゃんがくれたのは、真っ白いおとうふに、おぶつだん用のロウソクをさした、とてもシュールなものでした。
ぼくは、こう言ったセンスが、おじいちゃんとお母さんはよくにているなと思いました。
兄はそれを見て、
「わあ、お豆腐のケーキみたいだね!」
とよろこんでいましたが、ぼくにはそれをケーキみたいとは思えず、おとうふとおぶつだんのロウソクのコラボレーションなのだとしか思えませんでした。
こう言ったところが、ぼくがお母さんや兄、そしておじいちゃんと分かりあえないところだなと思います。でもそんなてんねんな彼らが大好きなので、自分までてんねんになってしまったら、きっと大好きだと思えなくなってしまいそうなので、このままでもいいかなと思います。
おとうふとロウソクのコラボレーションは、ロウソクを取ったら、ただのおとうふなりました。そしておしょうゆをかけたら、ただの冷ややっこになりました。でもおじいちゃんのおとうふは、りょかんやホテルにおろしているだけあっておいしいのです。ぼくはおじいちゃんのこのおとうふが大好きなので、とてもおいしく食べました。
でもざんねんなことに、おじいちゃんはおとうふ屋さんなのにおとうふがきらいなのです。きっと身近にありすぎて、そのよさが分からないんだろうなと思います。だからぼくは、やっぱり自分はてんねんじゃなくて良かったなとあらためて思いました。
おじいちゃんはおとうふを食べるぼくらを見て、ほそい目をもっとほそくしてうれしそうにしていました。
そしてめんきょを取ったばかりの兄と、車のはなしをいっぱいして、あきなの峠のせめかたなんかをおしえていました。
ぼくも二人の話をたのしくきいていましたが、だんだん話のないようが、せんもんてきな用語ばかりになってきたので、ちょっとたいくつになってしまい、しんぶんでもよもうかと部屋のなかをみまわしていると、おじいちゃんのそばに一冊の大きなざっしのようなものがあるのを見つけました。
「おじいちゃん、それなぁに?」
ぼくが聞くと、おじいちゃんはてれくさそうに笑って、そしてぼくらの前にその大きな雑誌を広げて見せてくれました。
それは、アルバムでした。
「今日はお前らのかーちゃんが嫁にいっちまった日だからな。ちょっと懐かしくなって見てたんだ」
そこにはぼくらの知らないお母さんがいっぱいいました。
まだ目がぱっちり開いている、わかいおじいちゃんにだっこされる赤ちゃんのお母さん。
男の子とけんかして、どろだらけの顔になっているお母さん。
おじいちゃんと、そしてたぶん亡くなったというおばあちゃんらしき、お母さんによくにた女の人にはさまれて、うれしそうに笑う、ぼくよりほんの少し大きな姿のお母さん。
「わぁ、お母さん、すごい小さいねー。何だか不思議な感じ」
兄のその言葉に、ぼくも同じきもちでいました。
大きなすがたのお母さんしか知らないぼくらにとって、お母さんにもこんな小さなすがたがあったんだと言うのは、あたりまえのことのはずなんだけど、ふしぎな感じがしました。
お母さんの小さいころは、兄とよくにていました。でも兄よりも、やんちゃな感じで、そしてお母さんが高校生のころのしゃしんを見ると、ぼくらは首をかしげてしまいました。
そこにうつるお母さんは、お母さんのはずなのに、ぼくらのお母さんには見えなかったからです。
「ねぇ、おじいちゃん。これ本当にお母さん?」
ぼくがそう聞くと、おじいちゃんは困った顔になりました。
「あー…、そん時はなぁ…あいつ、何もヤる気が無い時期でな。何言ってもぼーっとしてて、生きてんだか死んでんだか分かんねぇ時があったんだよ」
おじいちゃんは、ほっぺたを指でさすりながらそう言いました。
「何で、お母さん、こんなふうになっちゃったの?」
ぼくがまたそう聞くと、おじいちゃんは、ほんの少しだけさびしそうな顔になりました。
「…うちの奴…あいつの母ちゃん、お前らにとっちゃ、バアちゃんか。それが死んで、甘える人間にいきなりいなくなられて、ちょっと、あいつの中で大切なモンが凍っちまったんだろうな…」
おじいちゃんの言うことは、ぼくにはまだむずかしすぎてよく分からなかったけど、もしいきなりお母さんがいなくなってしまったらってことを考えると、ぼくは世界がおわったように感じるだろうから、きっとお母さんもそんなきもちになってしまったのかなと思いました。
ぼくらが悲しい顔になってしまったのにきづいて、おじいちゃんは空気をかえるように次のページをめくりながら言いました。
「…でもマァ、お前らの父ちゃんに会って、あいつも変わったからなぁ」
にがわらいでそう言った、おじいちゃんのさす指の先に、わかいころのお父さんといっしょに、なかよく笑っているお母さんのしゃしんがありました。
たぶん、お母さんの高校のそつぎょう式でしょうか?せい服をきて、そつぎょうしょうしょを持つお母さんのよこに、やけにきどったかっこうをしたお父さんが、ニヤけた顔でうつっていました。
ぼくはそのお父さんのすがたには不快感をかんじましたが、でもそのとなりでうれしそうに笑うお母さんの顔にはほっとしました。
そのお母さんのすがたは、今のお母さんとかわらない、キラキラしたすがただったからです。
「母さんは父さんに会って、幸せになったんだねぇ」
そのしゃしんを見て、兄がうれしそうに言いました。
はらただしいですが、ぼくも同じきもちでした。
その後のしゃしんのどれを見ても、幸せそうなお母さんのよこにはかならず、ニヤけた顔のお父さんがいたからです。
それらのじじつは、あきらかにお父さんがお母さんを幸せにしていると言うことをあらわしています。
今日、お父さんといっしょにでかけて行ったお母さんも、幸せそうな顔をしていました。
ぼくらの前でもお母さんは幸せそうな顔はします。
でも、お父さんといっしょのときの顔とはやっぱりちがいます。
『いつも母親やってるんだから、今日ぐらいは俺の恋人でいてくれよ』
そう言うお父さんに、いつもどくせんしてるくせに何を言ってるんだとこうぎしたかったのですが、お父さんの言いたいことはこう言うことなのかなと思いました。
そして、「お母さん」がお休みなのは、ぼくら子どもにとってさびしいことですが、でもお母さんが幸せそうで、そしてついでお父さんも幸せそうなら、一日くらいは、まぁいいかなと思いました。
お母さんが、お父さんだけのものになるのは今日一日だけで、きっと明日かえってきたら、僕らのお母さんにもどってしまうのだろうから。
だから今日一日。ぼくは不幸な子どもでもいいかなと思います。
サンタは子どものためにくるらしいけど、大人にだってサンタはきてもいいと思います。
お母さんにとってのサンタが、ぼくらであればいいなと思いました。
2005.12.22
画像提供 ぱんぷKING様

その夜は、そのままおじいちゃんの家にとまりました。
そして朝、家へかえると、ふしん者がリビングのソファで大の字になってお酒のびんをかかえたまま眠っていました。
サンタの服をきた、けいすけおじさんです。
ごちそうもケーキも食いちらかして、お酒でよっぱらっていびきをかきながら眠るおじさんは、なってはいけない悪い大人の見本のようでした。
あきれて言葉もでないぼくにかわって、兄がおじさんを起こしていました。ぼくだったらそのまま道ばたにでもほうりなげて、こおりついてしまったほうが、頭もスッキリしていいだろうなと思うのですが、兄はこんな悪い大人にもやさしく、
「啓ちゃん、こんなとこで寝てたら風邪ひくよ?」
と心配していました。
うなりながら起きたおじさんは、ぼくらの顔をみたとたんに怒り出しました。
「お前ら、どこ行ってたんだよ?!せっかく、俺がプレゼントを持って遊びに来てやったのによ」
…プレゼント。
どうやらけいすけおじさんは、ぼくらのサンタになるつもりだったようです。
「え、そうなの?ごめんね、啓ちゃん。おじいちゃんの家に遊びに行ってたんだ」
けいすけおじさんの言葉に、もうしわけなさそうに兄はあやまっていましたが、とてもではありませんが、ぼくはおじさんにかんしゃする気にはなれませんでした。
それよりもぼくは、サンタのかっこうでのんだくれるけいすけおじさんのクリスマスのありかたについてをなげきました。
ぼくは不幸な子どもだと思いましたが、世の中には不幸な大人がいっぱいいるのだなとじっかんしました。
そしてけいすけおじさんを見て、ぼくはそんなに不幸じゃないかも知れないと思えました。
人間、たまに下を見ることもひつようなのだなと学んだ日でした。